前回の記事はこちら!最後の将軍・徳川慶喜①~難しい時代に生まれて「敗者として終えた幕末」~
目次
謹慎生活のはじまり
慶喜、静岡へ
江戸城を無血開城した慶喜。
徹底抗戦を主張する幕臣らの声を抑え、新政府に従うことを表明します。
徳川一門や諸大名らの嘆願が功を奏し、慶喜は命を助けられます。
しかし、助命の条件の中に水戸で謹慎生活を送るというものがありました。
こうして慶喜は水戸に移り、謹慎することになります。
一橋家を相続するために旅立った水戸への帰郷は、とても寂しいものとなりました。
しかし、当時の水戸は大変な状況でした。
藩政の主導権を巡って攘夷派と佐幕派(幕府側)での対立が激化していたのです。
そんな状況で慶喜が水戸で生活するとなると、慶喜が対立に巻き込まれたり、利用されたりしかねません。
新政府と勝海舟ら慶喜の家臣は協議し、慶喜は駿府(静岡)への移転することが決まります。
水戸に帰郷してからわずか3か月。で慶喜は静岡に向かうことになります。
静岡での謹慎生活
慶喜は静岡に到着しましたが謹慎の身であることは変わりません。
まだ戊辰戦争は続いており、慶喜は宝台院というところで謹慎生活を続けます。
謹慎期間中、慶喜と会った渋沢栄一は、慶喜が6畳ほどの応接間で座布団も敷かず、汚れた畳に直に座って会談する姿を見て涙ぐんだと回想しています。
他人と会う応接間ですらこのような状況であれば、普段の生活がどれほどみすぼらしいものだったのか想像は難しくありません。
謹慎期間中、慶喜は時勢に関する批評は一切しませんでした。
慶喜の発言は日本に混乱を招く可能性があることを重々承知していたのです。
明治2年5月、ついに函館の五稜郭(ごりょうかく)に立てこもっていた幕府軍が降伏し、戊辰戦争が終わります。
その年の9月、慶喜はついに謹慎を解かれ、静岡での30年にわたる隠居生活が始まります。
これは慶喜33歳のことでした。

当時の謹慎生活は、今使う謹慎とは意味が違うのかな?

当時の謹慎は刑罰の一つだからね。門戸を閉めて人との接触や通信が禁止されるんだ!
政治への関心
慶喜が静岡で隠居生活をしている間、渋沢栄一は定期的に慶喜を訪問します。
しかし、慶喜は一切政治的発言をしませんでした。
渋沢も慶喜が政治に関することを話すのを嫌がっていることを察し、言わないように気を付けていました。
しかし、もともと政治に携わる二人。
ポロっと言ってしまうこともあったそうですが、慶喜はほとんど聞き流したり、相槌を打つ程度だったそうです。
慶喜は例えば世間では今これが流行っているよね、みたいな世間話は楽しそうにするそうなのですが、政治に関する批評は一切しない。
これは、やはり最後に自分が朝敵とされたことへのショックや、自分の立場というものを深く考えていたからだと思います。
これは明治5年に従四位に叙せられた後でも変わりませんでした。
従四位は天皇から与えられる位の一つ。位を叙せられるということは、事実上天皇からも許されたということなのですが、慶喜の心境を変えるほどではなかったようです。

本当は話したかったのかな??
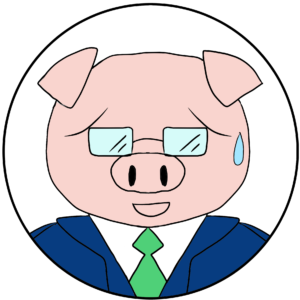
思うところは色々あっただろうね・・・でも何も言わないことを決めていたんだと思うよ!
趣味
慶喜にはするべき仕事もないので、静岡での謹慎生活の終了後、趣味を多数持つことになります。
もともと文武に長け、アグレッシブな性格。
時間を持て余してゴロゴロするようなタイプではありませんでした。
ここでは、慶喜が好んだ趣味についてご紹介しましょう。
油絵
幼少期から絵を書くのは慶喜の趣味でした。
そして、謹慎中に中島仰山(なかじまぎょうざん)から油絵を習います。静岡県立美術館のHPでは慶喜が書いた美しい油絵をみることができます。
鷹狩・銃猟
鷹狩は飼いならした鷹で獲物を捕らえる狩のことです。
歴史は古く、織田信長や徳川家康も大好きでした。
そして狩りつながりでいえば銃での猟も行っていました。
鷹狩も銃猟も本当に好きで、正月でも大晦日でもしょっちゅう猟に出ていました。
東海道線が開通した後は汽車に乗って猟に出かけたりもしたそうです。
刺繍
意外にも刺繍も趣味にしていました。
母親思いの慶喜は刺繍をして母である登美宮(とみのみや)にプレゼントをしました。
気に入らなければ刺繍を解いてしまい、自分で納得したものでないとプレゼントしないという妥協しない性格だったようです。
写真
若い間は猟や釣りを楽しんできましたが、やはり年齢を重ねると辛くなってくるのでしょうか。
50歳を過ぎたころからは猟や釣りの頻度が減っていきます。
ここで逆に増えてきたのがビリヤードや写真といった趣味でした。
特に写真はかなりハマったようです。
静岡の写真師徳田孝吉に指導を受けました。
慶喜の撮影した写真は今でも残っています。
被写体は家族や花、景色、建築物の他、そのころの庶民の生活風景や町の子供たちなども撮影しています。
写真集も出ていますのでご興味のある方はぜひ見てみて下さい。
自転車
慶喜が自転車に乗り回していたと新聞で報道されたことがあります。
明治20年2月5日付の静岡大務新聞で「昨今自転車を好み、日々洋服を着て市中を乗り回す」と書かれています。
子供たちの分も購入して一緒に出掛けたりしていたそうです。
サイクリングですね。
さすがに若い子供たちのほうが上手に乗っていたそうで、お供の者たちもついていくのに精いっぱいだったそうです。
静岡の清水まで10キロ以上走ることもあったそうなので、まさに乗り回す、という言葉がぴったりですね。
その他
ここに挙げた慶喜の趣味は一例です。
他にも、鵜飼、将棋、囲碁、洋画、能、小鼓などいろんなことにチャレンジしていました。
また、慶喜は基本的に他人との接触を避けていました。
しかし、新しい物や珍しいものを持ってくると、その人物には会ったそうです。
好奇心が抑えられなかったのでしょう。
来客から教えられたものは、蓄音機、元幕臣のフランス土産等です。
その他にも新しい蠅取り器を購入してみたり、家族で工場見学に行ったり、コーヒーを嗜んだりしたそうです。
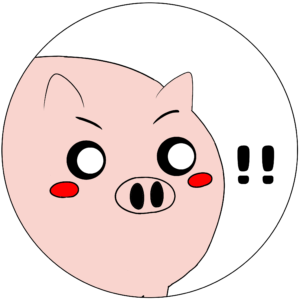
本当に多趣味だね・・・
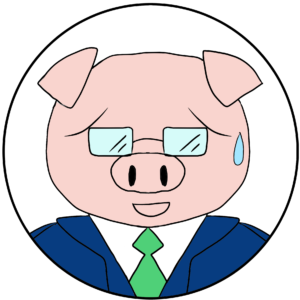
仕事することもできないし時間は大量にあるからね・・・
天皇家との関係
先述のとおり、明治5年に従四位の位を与えられていたので、政治的な名誉は回復していましたが、慶喜自身は明治天皇とはまだ会っていませんでした。
明治天皇が静岡に来るたびに、静岡県からお迎えに行くようにとの指示が出るものの、慶喜は拒否し続けていました。
これは、慶喜が拗ねているとかそういうことではなく、まだ自分の意思で行動できる立場ではないと慶喜が考えていたことが原因と考えられています。
決して天皇と対立しているわけではないものの、慶喜と明治天皇の間には目に見えない壁があったようです。
しかし、明治31年慶喜と明治天皇の対面が実現します。
この年から東京に引っ越した慶喜はかつての居城である皇居に向かうことになります。
会見の内容はわかりませんが、慶喜と明治天皇はお酒を酌みかわし、歓談したそうです。
明治天皇は伊藤博文に喜びを表し、慶喜も関係者や親族に喜びを表したとのことです。
幕末に朝敵という逆賊の汚名を受けていたという心のつっかえが取れたのでしょう。
慶喜にとっては真の意味で名誉が回復できた瞬間でもありました。
これ以降、慶喜は定期的に明治天皇に拝謁するようになります。
特に皇太子(後の大正天皇)とは頻繁に会い、月に1回程度のペースで交流するようになり、皇室との関係も完全に修復することができたといえるでしょう。
明治35年には華族の中でも最も位の高い公爵に叙せられました。

よかったね!ずっと気にはなっていたんだろうね・・・
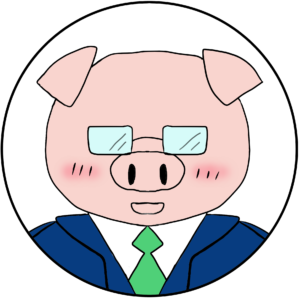
明治天皇も同じ気持ちだっただろうね・・・時間が経った後で会ったことも結果的には良かったかもしれないね
自動車にも夢中
明治45年7月の明治天皇の崩御(明治天皇が死亡)は慶喜にも大きな衝撃を与えました。
自分より若い明治天皇の死は慶喜の体調を狂わせるほどのショックだったようです。
そんななか慶喜の心を慰める出来事がありました。
大正元年にダイムラー製の自動車を手に入れたのです。
慶喜はまた自動車に夢中になります。
大正元年には警察署に自動車の使用届を提出。
そこからは自動車であちこちでかけまわりました。
自動車の使用届を出した約1年後の大正2年11月22日、慶喜は死去します。
明治天皇の死から立ち直れない慶喜に生きる喜びを与えた最後で最大の贈り物が自動車だったのです。
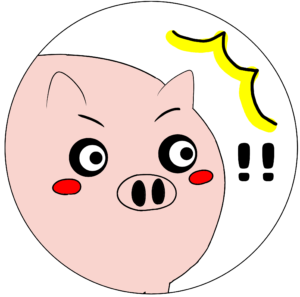
武士の時代から自動車の時代にって考えたら、すごい変化だね
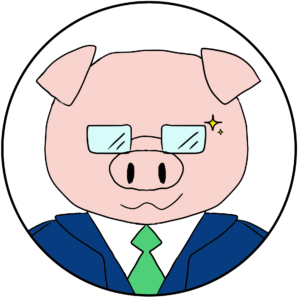
今でいうと太平洋戦争を経験した人がスマートフォンを見るようなものかもしれないね
最後に
最後の将軍・徳川慶喜のお話いかがでしたか?
前回の記事では激動の幕末で翻弄され続けた慶喜を書きました。
多くの人が知っている慶喜は明治維新までの最後の将軍としての慶喜です。
人によっては慶喜のことを卑怯な人間と思っていたり、明治という時代に恨みを抱えていたと考えていた人も多いかもしれません。
しかし、明治の慶喜を知ると、そのような評価にはならないのではないでしょうか。
どちらかというと、日本のために尽くしたにも関わらず、朝敵となったことをずっと引きずり、自分が日本の混乱を招かないように注意深くひっそり生活していたように感じます。
戊辰戦争で慶喜が大阪から江戸に敵前逃亡したといわれる事件も、抗戦を強く主張する会津藩の松平容保や桑名藩の松平定敬(まつだいらさだあき)を伴って大阪から去ることで、戦争を早く終わらせようとしたという見方もあります。
本当の慶喜の感情を今では想像することしかできません。
しかし、渋沢栄一ほどの人物が生涯をかけてその汚名を返上しようとしたことから、最後の将軍としての仕事を果たそうとしていたことは間違いのないことだと思います。

