前回からの続きです!
時代は明治を迎えます。
明治維新は大名、公家、市民問わず、その生活が一変します。
では長勲の生活はどのように変わったのでしょうか?

日本でこの時ほど劇的に生活が変わったことはないんじゃない?
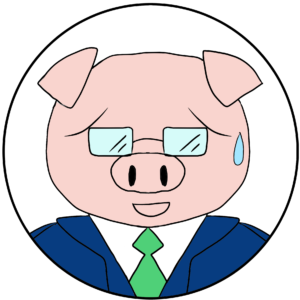
今みたいにメディアもないから、庶民たちは急激な変化を外国人に日本が乗っ取られた、と考えた人もいたみたいだよ
目次
明治の長勲
長勲の立場が大きく変わる
日本の政権自体は徳川幕府から朝廷に移っていた(大政奉還)のですが、藩の制度はまだ変わっていませんでした。
長勲は未だ広島藩の世継ぎだったのです。
そのような状況の中、明治2年、広島藩主・浅野長訓が隠居し、長勲は広島藩主となります。
そしてすぐに版籍奉還(土地や領民を朝廷に返す)を行い、封建的な制度が終了します。
そして、従来の公家や大名たちは「華族」となり、各藩主は「藩知事」という地方の長官になります。
さらにそのあと、「廃藩置県」が行われ、ついに幕藩体制が完全に終了します。
広島藩は広島県になったのです。
長勲はこの間、広島藩主、広島藩知事を経て、華族として東京に居住することになります。
長勲、洋紙製造を決意
東京に到着した長勲は、何をしようか考えます。
長勲のしたいことは、国家のためになる事業をして、社会に貢献したい、との一点でした。
そして、明治5年、なんと洋紙の製造業を始めることを決意します。
当時日本では和紙しか製造しておらず、洋紙は完全に輸入に依存していました。
しかし、今後洋紙の需要が伸びていくことは間違いなく、なんと現在の値段で126億円もする製紙機械を購入します。
さすがお殿様です・・・
さらに製紙工場も建設。
ちなみに、工場を建設するときは、煙や騒音などが近隣住民の迷惑にならないように、しっかり場所を選んで建設しました。
工場が稼働
明治7年にいよいよ製紙機械が稼働します。
長勲は製紙会社を「有恒社(ゆうこうしゃ)」と名付けます。
しかし、最初は失敗ばかり・・・
苛性ソーダの使い方を間違え、赤い紙ができたり・・・
井戸を掘ったら赤い水がでたり・・・
しかも当初は洋紙の需要が全くありませんでした。
それでも長勲は「長い目でみよう、いつか必ず必要とされる」と赤字にも動じなかったと言います。
西郷の戦争で特需に
それでも、徐々に需要は増えていき、有恒社の経営も上向いていきます。
そして、明治10年、有恒社の抱えていた在庫が全て売り切れるほどの事件が起きます。
西郷隆盛の反乱「西南戦争」が勃発したのです。
死を覚悟した西郷の反乱。
幕末から交友関係があり、協力し合っていたためか、政府から西郷を説得するように言われます。
しかし、長勲はどうすることもできません・・・
結果として、西郷は自刃しその生涯を終えます。
皮肉にも西南戦争を報じる新聞の需要が急増し、有恒社の洋紙の在庫がなくなるほど売れます。
長勲の心境は複雑でしたが、自分が決意した洋紙製造が世の中の役に立ったとの達成感も得たのです。
この後、高齢になると、長勲は有恒社から手を引きます。
有恒社は1924年に王子製紙と合併することになります。
長勲、イタリアにいく
長勲、40歳のときです。
現在の外務大臣にあたる外務卿・井上馨にイタリアへの全権公使を打診されます。
もちろん、今まで外国には行ったことありませんが、ワクワクして快諾します。
イタリアとは明治になってから交流ができたので、日本の顔になりえる人物が選ばれたそうです。
長勲は2年間イタリアに住むことになります。
明治15年、長勲は妻とともにイタリアに向かいます。
「イタリアは冬でも雪が降らず、いつも春か秋のようだ。」と感動しています。
さらに、芸術のレベルの高さ、食べ物や税制などにも感嘆しています。
明治17年に帰国が決まるまでイタリアを堪能し、イタリアの王族や政治家と交流を深めました。
さらに帰国途中では、フランス、イギリスに立ち寄り、ニューヨークでは自由の女神を見物。
さらにロシアでは白夜を経験しています。
世界を直に見てきた長勲は、日本が列強に負けないようにするため、日本の政治の在り方を真剣に考えるようになったそうです。

お殿様が経営なんて不思議だけど、持ち前の忍耐で乗り切ったんだね!
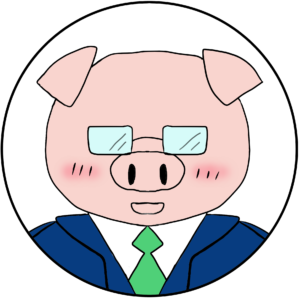
浅野長勲は単に最後の大名というだけでなく、とても大名らしい堂々とした人柄だったそうだよ!
4人の天皇に仕える
長勲は昭和まで生きたため、孝明天皇・明治天皇・大正天皇・昭和天皇に仕えたということになります。
さらに、単純にその時代を生きただけでなく、天皇から絶大な信頼を得ていました。
孝明天皇との関係は、前回の記事に書いたとおりですが、ここでは、明治天皇、昭和天皇とのエピソードも記載します。
明治天皇との関係
明治天皇とは、明治維新の当時まだ10代でしたが、当時から何度も会談を行っていました。
なんといっても孝明天皇の子なので、長勲も特別な思いがあったことでしょう。
明治になってから長勲が結婚した後、江戸城にて明治天皇とお酒を飲み交わしています。
この時、長勲は29歳、明治天皇は19歳。
(この時はお酒を飲む年齢に特に制限ありません!)
しかも、長勲はめちゃくちゃ酔ってしまったと回想しています。
天皇直々に頻繁に酌をして下さり、長勲は恐縮しながらもぐびぐび飲んでしまいました。
天皇は長勲の酒の強さに感心し、さらに天皇も顔を真っ赤にしていたそうです。
長勲はフラフラになり、人に助けられながら藩邸に戻ったそうです。
なんかほっこりするエピソードですね!
昭和天皇との関係
明治34年に生まれた昭和天皇。
長勲は昭和天皇の幼少期に教育係になります。
長勲は自身が幼少の頃、父に教わったことを昭和天皇にも伝えます。
その内容は
食べ物を粗末にしないように、よく噛んで食べなさい!
辛くても辛抱しなさい、将来国を背負って立つのですぞ!
学問だけでなく体も鍛えるのです!
なんか普通のお爺さんみたいですよね!
人として当たり前に必要なことが一番大事なんだってことを伝えたかったのかもしれません。
時はさらに流れ、昭和11年、長勲95歳の時、昭和天皇を訪問します。
昭和天皇は「もっと長く生きて、もっといろいろ話を聞かせてくれないか?」といったそうです。
長勲は感激して涙を流したそうです。
そのあと1時間ほど話した後、皇后やまだ幼い皇太子ともお会いしたとのことです。
おそらく長勲が皇太子と書いたのは現在の上皇陛下です。
ということは長勲は5人の天皇に会っていたということですね。
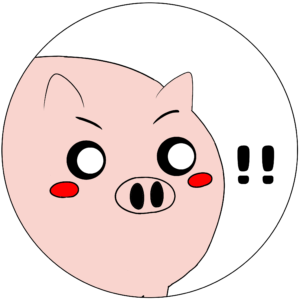
なんか昔のおじいちゃんって感じ・・・でも天皇陛下との信頼関係を感じるね!
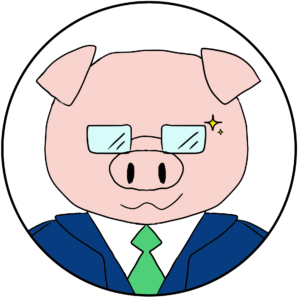
大きな変化の中にいて、変わらないことを教えられるのは人生経験がある長勲が適任だったのだと思うよ!
最後に
昭和天皇に最後に謁見した翌年の昭和12年、長勲は死去します。
亡くなったのは96歳。
日本史上において最も大きな変化があった時代に、常に日本を想い、全力で生き抜きました。
長勲は亡くなる前、「自叙伝」を記しています。
その中には今回の記事に書いてあることだけでなく、
・参勤交代時に乗る駕籠は体が痛い
・謁見の際、天皇陛下の顔は見てもいいが、将軍の顔は見てはいけない
・外様大名が謁見に来たときは将軍は座りもしない
・老中が将軍に謁見にきた大名を紹介するときは、ただ「安芸」とかと呼び、「安芸守」とは言わない
・江戸時代の家族の呼び方・・・などなど
その時代を生きた人間にしかわからないことがたくさん記されています。
自叙伝の最後を長勲は天皇への感謝で締めくくっています。
長勲死去から8年後、広島には原子爆弾が投下され、日本は太平洋戦争に敗戦します。
戦後、昭和天皇はGHQのマッカーサーに対し「自分の命と引き換えに国民の命を助けて欲しい」と言いました。
これは、孝明天皇から感じた日本に対する思いを、長勲がその後の天皇に伝え続けてきたことと無関係ではないかもしれません。

