目次
ベルリンの壁の建設
分断後のベルリン
ベルリンは東ベルリンと西ベルリンに分かれていたものの、ベルリンに壁のような物理的な「仕切り」はまだありませんでした。
東ドイツと西ドイツという二つの国ができた後でさえも、東西ベルリンの移動は自由で、地下鉄や鉄道も行き来していました。
さらに、境界を越えて通勤する市民も多く、毎日約50万人が境界を越えて移動するという状況でした。
東ベルリンの住人が西ベルリンに働きに行ったり、その逆もありました。
西ドイツと西ベルリン間の移動については、ソ連側が妨害することもありましたが、指定された道路や列車、航空機での往来は依然として可能でした。
流出する人材
ドイツは東西分裂後、西ドイツは資本主義、東ドイツは社会主義という体制とします。
東ドイツは「ドイツ社会主義統一党」の一党独裁体制となったのです。
しかし、東ドイツの一党独裁体制に不満を持つ人が現れ、西ドイツに逃亡する人が発生します。
それも毎年15万人から30万人というとんでもない人数でした。
当時、西ドイツと東ドイツは国境があり、自由な移動ができない中、唯一通行が自由なベルリンを通って西ドイツに向かったのです。
西ドイツは東ドイツ国民にも市民権を与えたため、西ドイツ側に入ってしまえば、逃亡は成功でした。
東ドイツはこの人材流出に頭を悩ませます。
特に医師や技術者という貴重な人材の流出は東ドイツの経済に悪影響を与えました。
ソ連の要求(1958年)
当時のソ連の指導者であったフルシチョフは西ベルリンを自由都市にするように通告します。
西ベルリンから英米仏を撤退させることで、東ドイツがベルリンを管理下に置けるようにしたかったのです。
もし英米仏が撤退しなければ、西ドイツと西ベルリンをつなぐルートを閉鎖するとも通告します。
そうなってしまうと、西ベルリンは完全に孤立してしまいます。
これは東ドイツからの人材流出を食い止めたいというソ連の意図でした。
しかし、英米仏及び西ドイツはこのソ連の要求を拒否します。
とはいうものの、特に英米はドイツ再統一のためにソ連と戦争するという考えは一切ありませんでした。
というのも、英米にとってドイツは第二次世界大戦時の敵国。
敵国の再統一のために自国の兵士を犠牲にするなどということはあってはならなかったのです。
戦争したくないというのはソ連も同じだったので、しばらくは何も起きず、膠着状態になります。
東ドイツの焦り(1961年3月)
このような状況の中、当時の東ドイツの書記長・ウルブリヒトは焦りを募らせます。
状況が膠着したところで、東ドイツからの人材流出は止まらず、経済的打撃を受け続けるためです。
この時の東ドイツは国家の存亡すら危うい状況でした。
ウルブリヒトはフルシチョフに英米仏の西ベルリン占領を終わらせることと、西ドイツと西ベルリンのアクセス管理権を要求します。
西ドイツと西ベルリンの往来を制限すれば、人口の流出が抑えられるだけでなく、西ベルリンが孤立するため、力をそぐことができると考えたのです。
そして、1961年初頭にはワルシャワ条約機構にも東西ベルリンの交通を遮断と、壁を建設を提案したのです。
しかし、フルシチョフはウルブリヒトに決断を待つよういいます。
当時、フルシチョフはアメリカの若き大統領、ジョン・F・ケネディとのウィーンでの会談を控えていたからです。
ウィーン会談(1961年6月)
1961年6月3日からウィーンで対峙するソ連のフルシチョフと、米国のケネディ。
ドイツの問題に関しては、フルシチョフは米英仏ソと西ドイツが東ドイツと平和条約を締結し、第二次世界大戦を終了させることを提案します。
しかし、ケネディは断固としてこれを拒否。
これは、東西ドイツが分裂したまま平和条約を締結してベルリンからアメリカを追い出したいソ連の思惑があるからです。
ソ連の目的はドイツを分断させたまま、ヨーロッパでの優位を保持すること。
フルシチョフはケネディに対し、「もし英米仏が平和条約を締結しなければ、ソ連が単独で東ドイツと平和条約を締結する」といいます。
戦争状態が終結すると、西ベルリンに英米仏が駐留するのは侵略行為であり、戦争状態になる、というのがフルシチョフの脅しでした。
ドイツ問題に関しては、ウィーン会談は何の進展もないまま、協議が終了してしまいます。
ベルリンの壁の建設(1961年8月)
ウィーン会談後フルシチョフは壁の建設に苦悩します。
東ドイツのためには、壁が必要。
しかし、壁など建設したら世界の社会主義に対する評判が悪くなる、と考えていたからです。
フルシチョフは、ベルリンの壁の建設を承認します。
東ドイツからの人材流出を止めて、東ドイツ経済を復活させ、かつ戦争を起こさないためにはこれしかなかったのです。
現代では、ベルリンの壁は東西を分断するために作られたものだと考えられがちですが、ベルリンの壁は、人材流出を防ぐという、あくまでも東ドイツ国内での政策の一環にすぎなかったのです。
1961年8月12日から13日にかけて、ベルリンの壁が建設されます。
壁は東部ベルリンの敷地内に建設し、西ベルリン側には絶対にはみ出さないこと、西ドイツと西ベルリンの地上ルートも航空ルートも妨害しないようくぎを刺します。
これは、アメリカを刺激しないための最低限の取り決めでした。
8月12日の深夜、東ドイツは国境の封鎖を始めます。
最初は有刺鉄線を張るところから始めました。
この壁の目的は東ドイツの人材流出を止めること。
1945年から1961年までの間に東ドイツから西ドイツに移った人はなんと約300万人。
そしてその半数以上が西ベルリン経由での逃亡でした。
これ以降東西ベルリン間で市民が行き来することは不可能になりました。

よくわからないけど、壁はあくまでも東ドイツから人を出さないようにするためで、「絶交する」みたいな意味ではないってこと?
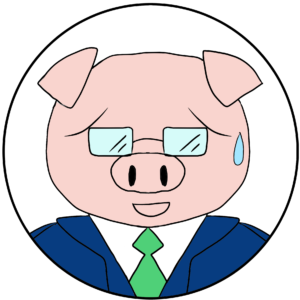
そうなんだ!壁の建設は第二次世界大戦から歴史の流れがずっとあるっていうことだね
ベルリンの壁建設後のドイツと壁の崩壊
社会主義国の弱体化
ベルリンの壁建設後、それでも壁を乗り越えて西ドイツに向かう人は後を絶ちませんでした。
運よく逃げきることができた人もいますが、東ドイツの国境警備隊に逮捕されたり、川を泳ぎ切れずに溺死したり、射殺される人も多くいました。
1970年代にはオイルショックなども起こり、不況がより加速します。
1972年には東西ドイツ間で国交ができ、東ドイツは西ドイツから経済援助を受けますが、これ以降は経済援助に頼った状況になりました。
1980年代に入ると、近隣の社会主義国であるハンガリーやポーランドで社会主義からの脱却を図ろうとする声が上がり始めます。
東ドイツはソ連にとって社会主義国の最前線。
東ドイツまで社会主義を脱却するような運動が沸き上がることは避けなければなりませんでした。
そこでシュタージ(秘密警察)を動員し、思想統制や国民の束縛を強化します。
ゴルバチョフの登場
1985年、ソ連は新しい書記長にゴルバチョフ氏が就任します。
ゴルバチョフは「ペレストロイカ」という政策を進めます。
ペレストロイカは今までの政策の失敗を直視し、その状況を打破するために策定されたものでした。
しかし、ペレストロイカはあくまでも社会主義体制を保持したまま変革を行うことでした。
ゴルバチョフには東ドイツを含めた社会主義諸国にもペレストロイカの導入を勧めます。
受け入れた国もありましたが、東ドイツはペレストロイカの導入を拒否し、東ドイツの最高指導者であるホーネッカーはゴルバチョフと対立します。
ベルリンの壁の崩壊
カギになったのはハンガリーの政策変更でした。
ハンガリーは社会主義国家でしたが、1980年代には民主化に向けた声が上がり始めます。
1988年に首相に就任したネーメトは1989年5月にハンガリーとオーストリア間の鉄条網を撤去します。
オーストリアは社会主義国家ではありません。
この結果、東ドイツ国民は、ハンガリーからオーストリアを経由して西ドイツに入るというルートができあがったのです。
こうなってくると、ベルリンの壁に意味がなくなってしまいます。
このようになっても、ホーネッカーは改革を行おうとしないため、ついに失脚させられます。
1989年11月9日、東ドイツの新執行部が出国規制案について話し合います。
新政権の広報担当者は記者会見で「すべての国境通過点から出国が認められること、これが遅滞なく行われる」と発表してしまいます。
しかし、この時はまだ出国の自由は確定事項ではなかったので、広報担当者が事前にこのように話すよう指示があったとも、本当に混乱していたともいわれています。
広報担当者の発言はベルリンの壁がなくなるという衝撃的な発言でした。
その日の夜には東ベルリン国境に市民が殺到、国境警備隊も出国ゲートを開放せざるを得ませんでした。
そして11月10日、重機などで壁の破壊され、28年間存在したベルリンの壁は崩壊しました。
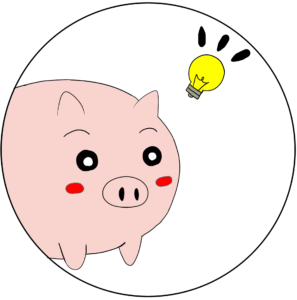
なんか崩壊する時ってあっけないんだね・・・社会主義の限界を感じた人が多かったっていうことだね・・・
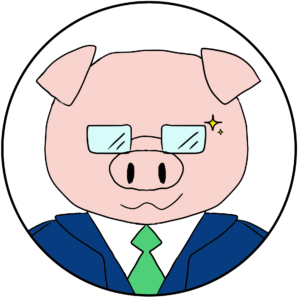
第二次世界大戦後に社会主義国と資本主義国では経済発展の度合いが違った。経済的な勝者という意味で答えは出たんだ
最後に
ドイツの第二次世界大戦後からベルリンの壁の崩壊までを駆け足で取り上げました。
アメリカとソ連には共通の認識がありました。
それは、直接の戦争だけは避けなければいけないこと。
互いに所有している核兵器がこれほど直接戦争の抑止力になったことはないかもしれません。
とはいえ、あまりに多くの代理戦争が発生してしまったこともまた事実です。
東ドイツの経済成長はかなり長い間とまりました。
東ドイツの国民車「トラバント」は30年間特にモデルチェンジもされませんでした。
ベルリンの壁崩壊後、西ドイツのBMWを見た東ドイツの人はその性能の違いに衝撃を受けたようです。
1990年10月3日、東ドイツは西ドイツに吸収され、消滅します。
現代でも旧西ドイツの地域と東ドイツの地域は経済格差があるそうです。
しかし、ドイツは何度も敗戦でズタズタになりながらも復活を遂げてきた国なので、そのような地域経済格差もいずれなくなることでしょう。

